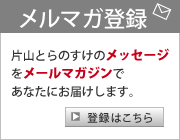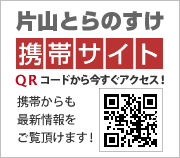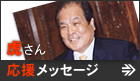メールマガジン
2011.04.29
571号 大震災の復興体制について
東日本大震災にかかる本年度第一次補正予算は5月2日に成立の見込みです。大震災発生から50日を過ぎ、予算成立で新たなステップに入って来ましたが、それにしても、復興体制のモタつきが心配です。色んな議論が錯綜して、いまだまとまっていません。
私はこれまで、口を酸っぱくして、専任大臣をつくって権限や情報を集中、有能なスタッフを集めてサポートさせ、そこを参謀本部に、決定したことは所管省庁に責任を持って実行させる、判りやすい体制にすることだと言って来ました。役所の新設など、それこそ行革に反し二重行政になるだけで、愚の骨頂です。
過去をみれば、大正12年9月1日発生の関東大震災の際は、「帝都復興院」ができましたが、帝国議会との摩擦等もあり5か月弱で廃止、後は、内務省の外局の「復興局」へ移管され、6年間存置で幹線道路など都市整備に努めました。
平成7年1月17日発生の阪神大震災では、「復興庁」立ち上げ論も一部あったものの、結局、行革や地方自治尊重の観点から、復興対策本部(本部長は首相で全閣僚参加)となり、5年間の時限組織として役割を果たしました。
今回の東日本大震災は、被害が広域かつ大規模であり、地震、津波、原発事故、風評被害の四重唱であるうえ、行政機能を喪失した自治体が多いことから、これまで以上に国が前面に出る必要があることは言うまでもありません。
しかしながら、具体的な復興を進めて行くには、やはり住民と市町村の意向を尊重しつつ、自治体である県を中心にしながら、国が、現地本部等も強化して全面的に協力して行く方式が正しいのではないかと考えています。
2016.07.09
2016.06.29
TV出演(BS日テレ、『深層NEWS』)のお知らせ2016.6.29.22:00
2016.06.25
TV出演(BS朝日、『激論!クロスファイア』)のお知らせ2016.6.25.10:00
2016.06.21
TV(テレビ朝日、報道ステーション)出演のお知らせ2016.6.21.21:54
2016.06.21