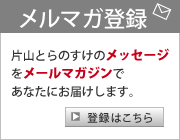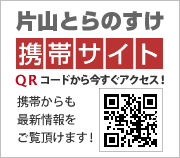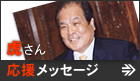メールマガジン
2010.03.30
463号 食料・農業・農村基本計画について
3月29日、食料・農業・農村政策審議会は、今後10年間の農政運営の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計画」を赤松農水相に答申しました。30日の閣議で決定される予定です。
基本計画は、平成12年に初めて策定され、今回が2回目の改定となります。
昨年の衆院選の民主党のマニフェストに掲げられた政策が大幅に取り入れられ、食料自給率(カロリーベース)を平成20年度の41%から平成32年度に50%に引き上げるなど自給率の向上を最優先の目標とするとともに、目標実現のため、戸別所得補償制度や農林水産業と加工・流通産業を融合させる「6次産業化」の推進などを盛込んでいます。
基本計画は、世界人口の増加や新興国の経済発展によって食料需要が増加する一方、地球温暖化による水不足や砂漠化の進行などで食料価格は上昇傾向で維持すると予測、その上で、食料の安定供給を将来にわたって確保するため、自給率を最大限向上させることが必要としていますが、この点は誰も異論がないでしょう。
そのため、農地の延べ作付面積を平成20年度の426万haから平成32年度は495万haに、耕地利用率を92%から108%に引上げ、品目ごとの32年度の生産目標数量もコメ粉や飼料用を含むコメが975万トン、小豆180万トン、大豆60万トンなどと大幅な増産をめざし、畜産物は、数量でなく飼料の国産化によって自給率を高める計画です。
問題は、計画に自給率の目標は書かれているものの、その実現のプロセスが不明で、施策、予算等の裏付けがないうえに、これまで力を入れて来た担い手育成やインフラ投資などが一方的に打切られていることにあります。
2016.07.09
2016.06.29
TV出演(BS日テレ、『深層NEWS』)のお知らせ2016.6.29.22:00
2016.06.25
TV出演(BS朝日、『激論!クロスファイア』)のお知らせ2016.6.25.10:00
2016.06.21
TV(テレビ朝日、報道ステーション)出演のお知らせ2016.6.21.21:54
2016.06.21